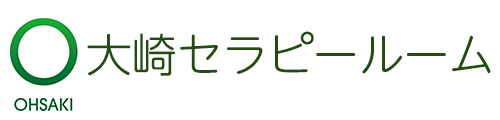仕事や人間関係の過度なストレスで、身体や心の不調が出ていませんか。
適応障害には、眠れない、朝起きられない、動悸がするという日常生活は送れる軽いものから、仕事に行けない、人間関係が上手くいかない、短期間に何度も転職を繰り返してしまうといった、重いものまであります。
適応障害を放っておくと、心や身体の不調がいつまでも続いたり、被害的な考えに囚われ外に出れなくなったり、衝動的な問題行動を起こし人間関係を壊すことが生じるようになります。
そのような適応障害を抱えている人に、心理カウンセリングは有効に働きます。
この記事では、適応障害に関する説明と、その対処や治療法について説明します。また大崎セラピールームで行っている適応障害へのカウンセリングを紹介します。
目次
適応障害とは
適応障害とは、仕事(学業)の不適応や、環境の変化、喪失体験などのストレスによって、体と心に不調をきたす疾患です。ストレス障害とも呼ばれています。
適応障害は、ストレスの元になっている場所から離れ、休みをとれば、調子は戻ります。しかし、また、元の場所に戻って、同じようなストレスがかかると、不調を訴えるようになります。
適応障害は、うつ病と間違われることがあります。うつ病の症状が、抑うつ感、焦燥感、やる気が起きない、不眠など適応障害の症状と似ているからです。しかし、うつ病はストレスの原因と思われる場所から離れても、これらの症状はなくなりません。この点が適応障害とうつ病の違うところです。
適応障害は治療をしなければ、たとえ職場に復帰したとしても、また休職を繰り返し、職場に居づらくなり、退職せざるを得なくなることもあります。そのため、症状を自覚したらできるだけ早期の治療が必要です。
適応障害により、心身がどのような不調を訴えるか解説していきます。
適応障害の症状
適応障害は、ストレスによって心身の不調や問題行動を起こすなど様々な症状を引き起こします。
心の不調を感じるようになる
気分が落ち込む、以前楽しめたことが楽しめない、やる気が起きない、将来に希望が持てない、などの心の不調を感じます。
心の不調によって、抑うつ状態になります。
心の不調が感情、行動に悪影響を及ぼすようになる
イライラ、焦燥感、過度な不安や心配、急に涙が出てくる、怒りを人にぶつけてしまうなど、感情や行動に不調が表れます。
感情をコントロールすることが難しくなると、人間関係のトラブルになりやすくなり、人に会いたくなくなります。その結果、自分の生活の行動範囲が制限されます。
体調不良を起こす
不眠、朝起きられない、動悸がする、パニックを起こす、集中力の低下、など体調不良に表れます。 心の不調が体調の悪化を引き起こすようになります。
問題行動を起こしてしまう
引きこもる、会社を無断欠勤してしまう、人と喧嘩をして人間関係が壊れる、傷害事件を起こしてしまうなど、問題行動へと発展していくことがあります。
適応障害が重症化すると、感情のコントロールが難しくなり、衝動的な行動を抑えられなくなり、自分や他人を傷つける行動を取ってしまうことがあります。
適応障害の原因
適応障害の主な原因は、ストレスですが、代表的なものを紹介します。
環境への不適応
引越し、転職、転校、など新しい環境での生活に不安や緊張を強いられたり、その環境変化についていけず、適応障害を発症することがあります。
人間関係のトラブル
職場、学校、家族内での人間関係の悩みやトラブルで、そこの人たちと会いたくない、しかし行かなければならないという葛藤状態が生じて、適応障害が引き起こされます。
人生の喪失体験
親族の死、離婚、失職、大きな病気、など人生における大きな喪失体験は精神に大きなストレスを与えます。悲しみや苦しみから抜けられずに、適応障害になることがあります。
過剰適応をしている
過剰適応によって、適応障害になることがあります。過剰適応とは、周りの評価を気にして、自分の感情や意見・行動を抑え込んでまで、周りに合わせすぎてしまうことです。
人から認められることで自分の安心や評価を得ようとするため、人に合わせることが目的化します。
周りに合わせるのが苦しいのにも関わらず、人から見捨てられるかもしれない、という恐れから、人に合わせすぎることを止められなくなります。
完璧主義
人から文句を言われないように、何度も自分の仕事をチェックして、完璧なものに仕上げようとします。
物事はこうあらねばならないと厳しいルールを自分に強いて、それに自分を押し込めようとします。
そのため、一つの課題に時間がかかり過ぎてしまい、やることに手が回らなくなり、仕事をするのがおっくうになってしまいます。
やらなければいけないのに、手が付けられないという悪循環にはまって行き、適応障害を引き起こします。
適応障害の対処法・治療法
適応障害の治療法の代表的な対処法、治療法を紹介します。
薬物療法
薬物療法は、出ている症状に対して、医師が診断をして薬が処方されます。
抑うつが見られるのであれば抗うつ剤が処方され、憂うつな気分、不眠、痛みなどが改善されます。
不安やパニックがみられるのであれば安定剤が処方され、不安を和らげ、気持ちを落ち着かせます。
不眠があれば睡眠導入剤が処方され、眠れるようになります。
身体の痛みがあれば鎮静剤などが処方され、痛みの緩和がなされます。
休養を取る
適応障害によって、身体も心も疲労困憊して、傷ついていますので、しっかりと休養を取ることです。
過剰に仕事をしていた場合は、おそらくは食事も睡眠も、気にかけることができず、生活のリズムは不規則だったと思われます。
栄養バランスの取れた規則正しい食事をとる、早寝早起きする、よい睡眠をとる、きもちのいいお通じがあることが身体の健康回復を図ります。
ストレスの元から離れ、休養を取り、身体の健康が取り戻されると、適応障害はかなり改善されます。
環境を調整する
仕事で強いストレスを受けているなら、職場と話しあって、負荷のあまりかからない仕事にしてもらう、関係の悪かった人間関係からは外してもらうなど、職場環境に配慮してもらう必要があります。
また、仕事を休んでいた方が復職した場合も同様です。ストレスを受けることで、適応障
害が繰り返されてしまうことになるので、環境調整をすることが重要になります。
カウンセリングを受ける
仕事を休むことの不安、将来の不安などを一人で抱えることは、大変つらいことです。カウンセリングではその不安を聞いてもらうことができます。
自分の気持ちをカウンセラーに受けて止めてもらうことで、不安を自分で受容することが出来、安心感を得られるようになります。
適応障害のカウンセリング
適応障害に対して行うカウンセリングで代表的なものを紹介します。
出来ることと出来ないことを分ける(限界設定)
適応障害になっている方には、自分と他人の責任や、やるべきことの境界があいまいになっていることが多いです。そのため、自分が出来ること、自分が出来ないこと、自分の範囲内なこと、他人の範囲なことを分けてみます。
この限界設定は簡単なようでいて難しい面があります。理性ではわかっていても、感情面で境界線を付けるのは、困難なことだからです。
他人が苦しんでいる、困っているというのは他人の感情、領域です。他人の領域を、自分がすべて助けることはできません。自分の出来ることに境界線を引いて、人と自分の領域を分けることを学ぶ必要があります。
認知行動療法をもとに自分の感情・行動を振り返る
認知行動療法では、自分の無意識に、信念の核(コアビリーフ)があり、それに基づいて感情が沸き起こってくると考えます。
例えば
「言われたことをきちんとやらないと、人から無能と思われ、自分の評価が落ちる」という信念の核があるとします。この信念から外れたことをすれば、不安が湧いてきます。その不安が出てこないように言われたことはしっかりと実行します。
しかし、自分の感情を抑圧してまで、無理に人の言われたことをするようなことが続くと、やらなければいけないのに、身体が動かない、朝起きられない、などの適応障害の症状が出来ています。
認知行動療法では、その信念の核に対して、
「それをしなかったからと言って、自分の評価は下がるのか」、
「自分の仕事はきちんとこなしているので、それは無能ではないのではないか」
と、客観的に自分を見つめてみます。
そうすることで、
「自分は思ったほどダメじゃないし、無能ではない」
と理解できると、不安の感情も下がっていきます。
認知行動療法では、自分の思い込みや、感情や行動をメモに取ったり、ノートに付けたりして、自分の行動や感情を振りかえります。そして自分の無理な考えや行動を修正していきます。
アサーティブトレーニング(自己主張トレーニング)
Noと言えるようになる。
例えば
「それはできません。」
「先に帰ります。」
「それは自分の仕事の範囲ではありません。」
など、Noという練習をします。
今までやったことがないので、当然Noということに抵抗が出たり、不安になります。
まず、カウンセラーとロールプレイをしてみて、Noをいう練習をします。次に、実生活の中で実践していきます。実践したあと、自分自身の感情や行動の変化、さらには人間関係が変化をカウンセラーにフィードバックします。
適応障害に対する大崎セラピールームのカウンセリング
適応障害になってしまい、人間関係がうまくいかない、休職に追い込まれるなどしたら、この先大丈夫だろうか、という不安や焦りが出るのは無理もないことです。
大崎セラピールームでは、不安や心配を一緒に受け止めながら、この挫折をきっけかにして、自分らしい人生を送っていくチャンスに変えていくお手伝いをします。
具体的にどんなカウンセリングをするか紹介します。
今の状態を受け入れる。
まず、現在抱えている不安や心配を自覚し、受容することから始めます。
この不安に自覚的にならないと、衝動的な行動に出てしまいます。例えば、仕事の不安から逃れるために、早急に職場に復帰して、遅れを取り戻そうとすると、結果として、自分にストレスをかけることになり、また調子を崩したりします。
そうならないためには、不安や焦りは当然のことだと自分の感情や状態を受容していくことが大事です。
人間関係のパターンに気が付く
今までの人間関係や行動のパターンを調べます。
・人の顔色ばかり見て、それに沿った行動を無意識に取っていないか
・場が緊張しないように、自分が我慢してその場を和ませていなか
・その場から排除されないように、過剰にいい人を演じていないか
・人に相談せずに、仕事を自分で抱え込んでいないか
その人がこれまで、無意識に培ってきた、人間関係のパターンがあります。
適応障害になったということは、今までのパターンや人間関係の処世術が使えなくなっていることを意味します。今までの無理なやり方を手放し、それ以外の方法をカウンセラーと一緒に探していきます。
身体感覚を取り戻す
適応障害の方の多くが、不眠や、食欲がない、お腹の調子が悪いなど身体不調を訴えています。
バランスが崩れた身体感覚を取り戻す必要があります。
基本的に、美味しい食事、ぐっすり眠れる、すっきりとお通じがある、というのは気持ちが良いもの(快感)です。
快食・快眠・快便があって、身体が気持ちいい、という感覚は、人の感覚ではなく、自分主体の感覚です。この基本的な健康に基づく、自分主体の身体感覚を取り戻していきます。
自分の感情を取り戻す
自分の湧いてくる感情を抑圧することで適応障害は進行します。
特に、怒り、嫉妬、恥、悲しみ、寂しさ、といったマイナスな感情は抑圧してしまう傾向があります。
湧いてくる感情はすべて肯定し、自分はこう感じていいんだと、自分を肯定・受容していく必要があります。
身体感覚と同様に、自分の感情も自分のものです。感情を取り戻していくことが自分主体に生きるための大事なプロセスになります。
親のいい子を止める
人の期待に応えることで、承認を得て、自分の存在が認められることで、自己評価を得ていると、ずっと人の評価に怯えることになります。
そのような生き方の根は、幼少期の親との関係まで遡ることが出来ます。親のいい子をやることで、親から承認を得て、認められることが愛情だったと思ったかもしれません(これを条件付きの愛情といいます)。
ずっと親のいい子をやって、親の期待に沿うような生き方をし続けてきたので、社会人になっても周りの期待に応えることで、自分の居場所や、自己評価を得てきたことでしょう。
適応障害になったということは、そのやり方が通用しないことのサインになります。
これを機会に、適応障害だったときの人生観をリフレーム(考え方の枠組みを変える)し、人の評価で生きるのではなく、自分主体の人生を歩んでいくきっかけにしていきます。
人生の再構築
今後、自分の人生をどう歩んでいいかカウンセラーと一緒に考えてきます。
自分の身体感覚、感情を取り戻し、今までの人間関係を見直し、自分主体の人生をどう生きたいのか、カウンセラーと一緒に考え、伴走してもらいながら、自分の人生を再スタートしていきます。
メリット
カウンセリングが有効に働くと以下のような効果が現れます。
・適応障害に罹ったことをポジティブに捉えられます。
・人の目や評価がそれほど気にならなくなります。
・自分らしい人生を歩んでいけるようになります。
効果
カウンセリングが有効に働くと以下のようなメリットが得られます。
・焦りや不安、心配の囚われが少なくなります。
・心の落ち着きを取り戻すことが出来ます。
・自分を肯定的にとらえられるようになります。
費用
最初の6回から8回くらいでカウンセラーとの信頼関係を作り、カウンセリグがクライアントに有効かどうかを見極める期間の見安にしてください。(最初は一週に一回のカウンセリングで一か月間ほど、関係や症状が落ち着いてきたら二週間に一回を一ヶ月から二か月で6万から8万円)
それから、だいたい6回を目安として、その人の課題、解決したいテーマを取り組んでいくカウンセリングを行っていきます。(2週に一回のカウンセリングで3ヶ月、6万円)
およそ半年くらいを目途に考えてみてください。
適応障害に悩んでいる方、大崎セラピールームにご相談ください。
過度に、職場に適応しようとして、適応障害になったのですから、同じ環境に復帰して、同じような過剰適応(がんばり)で、乗り切ろうとしても、同じ適応障害に陥ってしまいます。
適応障害は、今までの生き方や、考え方では、上手くいかないよ、と伝えてくれているサインです。そのサインを見落とすと何回も同じことを繰り返してしまいます。
ここで一度自分の働き方や、考え方、また自分の人生に対する考え方や態度を見直してみませんか?
これを契機に、自分の生き方を柔軟に変化させていくチャンスにしていきましょう。
きっと、あなたらしい人生を送る、きっかけになってくれるはずです。
あなたが、自分らしい人生へを歩んでいくのを、大崎セラピールームがお手伝いさせていただきます。